about Branding
ブランディングとは
何か?
〜ブランディングは「企業」で差別化を図る時代へ〜
目次
ビジネスにアドバンテージをもたらす「企業ブランディング」
日本のビジネスシーンへ、ブランドやブランディングという概念が本格的に導入されてから約20年が経過しました。
この動きは現在では大企業だけでなく中小企業にも拡がりを見せ、マーケティングおいてブランディングという言葉自体も広く定着してきた印象があります。ここでのブランディングとは、BRAND=あるべき姿を規定し形にし、ING=あらゆる活動を通じてそれを伝達浸透させることと定義しています。
日本企業は、先行する商品やサービスに対して改良、改善を加えることで競争優位を保つ「製品差別化戦略」を展開してきました。まだ企業間で提供する製品に大きな差があった時代にはうまくいっていたのですが、技術の平準化とともに「どこも大きく変わらない」状況となり、有効に機能しなくなってしまいました。こうした「同質化競争」が進んだことで、多くの企業はそのマーケティング活動において「ブランド」に差別化の源泉を求めるようになったという経緯です。
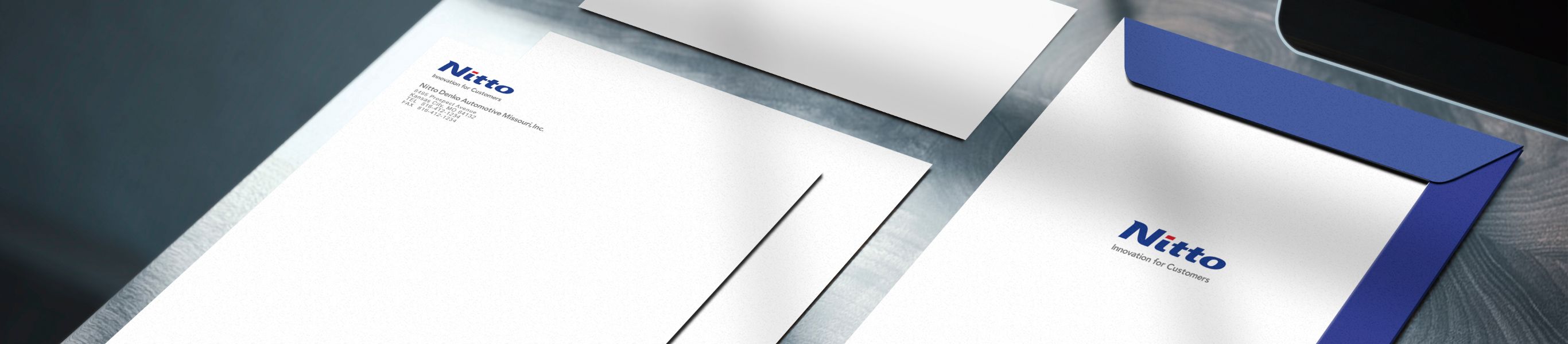

「商品・サービス」軸のマーケティングではなく、「企業」そのもので差別化
しかもそのレイヤーは「商品・サービス」ではなく、「企業」や「事業」で差別化を図ろうとする「企業ブランディング」を行う企業が多いというのが特徴です。今、企業に求められているのは「社会」との関係づくり、簡単に言えば「社会のためになるか」という視点での企業運営です。これを考えるグローバルな共通言語がSDGs。このため従来は個々の事業や製品、サービスを束ねる企業の「良さ・強み・特長」をいかに伝えるかが焦点でしたが、現在ではこれに加えて、個々の事業や商品、サービスの背後にある企業としての「理念・哲学・良心」の表明が求められています。高度に学習した先進的な消費者は、モノ選びの際に「どういう社会を創ろうとしている会社か」「社会にどう役立っている会社か」「環境に配慮している会社か」といったことを重視します。企業としての「人格」が問われていると言っても過言ではありません。まずはこの「ありたい理想の姿」を鮮明化することが必要です。近年経営のバズワードでもある「パーパス」もこうした背景から出てきたものです。

図1 企業ブランディングの訴求のコア
企業ブランディングは顧客向け、社員向け、両輪で行う
「企業ブランディング」とは、すべてのステークホルダーへ自社の魅力や持ち味を伝え、望ましい態度や行動を引き出していくための体系的な活動です。顧客や投資家、社会へ向けた対外的な活動と、社員・スタッフへ向けた対内的な活動が両輪になります。実際に企業ブランドは各現場の社員・スタッフ一人ひとりの態度や行動によって作り上げられます。そういう意味では対内的なインナーブランディングがより重要になっていると思います。
「企業ブランディング」は一般的に以下の図2のステップで進めていきます。どのステップも重要ですが、最重要工程は「ブランドコンセプトの構築」です。この上流のコンセプトがずれていると、思ったようなブランディングの効果が得られないからです。

図2 企業ブランディングの推進力
企業ブランドコンセプトは「MVV型」が主流に
従来コンセプトは、図3のVALUE=提供価値に軸足を置いた「VMV型」が主流でした。弊社でもこの考え方に基づいてコンセプトを作成してきていました。しかし、社会との関係がより求められている現在は、MISSION=使命に軸足を置いた「MVV型」に完全にシフトしてきています。「MVV型」のコンセプトは図4のフレームワークで策定します。このフレームワークの優れたところは、横軸に「行動」だけでなく「目的」を置いたことにあります。その事業は何のためにやるのかを考えることは、自社のパーパスを考えることになり、時代が求めるコンセプトが導かれやすくなります。

図3 企業コンセプトはVMV型からMVV型へ
従来コンセプトは、図3のVALUE=提供価値に軸足を置いた「VMV型」が主流でした。弊社でもこの考え方に基づいてコンセプトを作成してきていました。しかし、社会との関係がより求められている現在は、MISSION=使命に軸足を置いた「MVV型」に完全にシフトしてきています。「MVV型」のコンセプトは図4のフレームワークで策定します。このフレームワークの優れたところは、横軸に「行動」だけでなく「目的」を置いたことにあります。その事業は何のためにやるのかを考えることは、自社のパーパスを考えることになり、時代が求めるコンセプトが導かれやすくなります。

図4 MVV型コンセプト策定フレーム
一橋大学ビジネススクールの名和高司先生は、パーパスを含む優れたコンセプトを掲げている企業の共通点を3つに整理してくれています。
①「ワクワク」
思わず心がワクワクしてくるような目標が掲げられていること
②「ならでは」
自社ならでは固有の価値が示されていること
③「できる!」
全く手の届かないものではなく、頑張ればできるものであること
筆者は、実際のブランディングの仕事の中で必ずこの話を引用しています。中でも1番大事なのは①の「ワクワク」だと。人は理屈ではなく感情で動くものであり、社員のポジティブな気持ちを鼓舞できるようなものでないとダメだと申し上げています。みなさんの会社の企業理念や企業コンセプトはどうですか。この3つのポイントを満たしているかを一度チェックしてみてください。
TCDは、50年にわたりブランディング実績を蓄積、100業種を超える経験をしてきました。「ブランディング」に必要となる市場調査、コンセプトの立案からブランド戦略に則した最適なアウトプットの構築まで、プロジェクトの一員となって経営に必要となるブランディングをサポートいたします。

