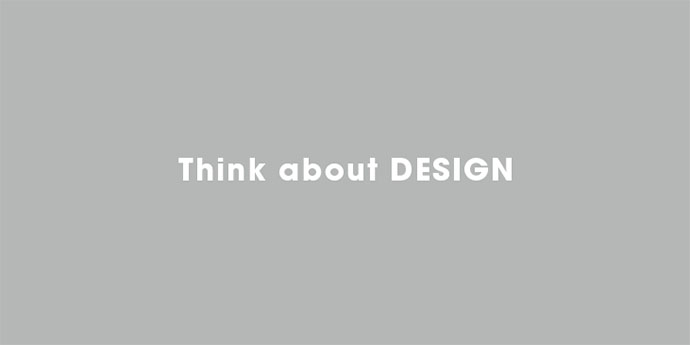2023.08.07
企業ブランディング動向
「パーパス経営」とは何か?
 生山 久展 株式会社TCD ブランディングオーソリティー
生山 久展 株式会社TCD ブランディングオーソリティー

企業ブランディングの最重要工程はコンセプト策定
私はこれまでに多くの企業ブランディングを経験してきました。その成否を分けるポイントは何かと問われれば、迷わず最上流工程の「コンセプト」の策定と答えます。企業ブランディングにおけるコンセプトとは、平たく言えば「自分たちは何者で、何のために、何を目指し、どこへ向かうのか」を言葉化したものです。一般的には、ミッション、ビジョン、バリューの定義から始めます。この頭文字をとってMVVと呼ばれています。
ただし、コンセプトを言葉化すればすべてがうまくいくわけではありません。中には非常に魅力的なコンセプトで競争力に直結している場合もありますが、大半は外部の人の心を動かすような次元のものには達しません。つまりコンセプトの一義的な役割は、内部=社員の納得や共感を引き出すことになります。社員の意識を統一し、ここから生み出されてくる製品・サービスや社員の行動に一貫性が感じられた時に、はじめて外部の人にもその価値を伝える役割を果たすことができるものだと思っています。
パーパスは今や企業経営の重要キーワードに
さて、コンセプトを構成する要素であるMVVですが、企業によってその言葉使いがバラバラで、「これビジョンじゃなくてバリューじゃない?」と思うこともしばしばあります。基本的には社員の納得と共感が得られれば目的は達成されるわけですから、教科書的な言葉使いはこうあるべきといったことを押し付けることはあまり意味のあることではないですね。
私たちTCDでは、MVVを以下のような定義してきました。
1.ミッション ブランドが果たすべき使命
2.ビジョン ミッション実現のための理想の企業像
3.バリュー 社員と共有したい価値観や行動
これらに加えて、企業ブランディングで注目を集めている概念が「PURPOSE=パーパス」です。今や企業経営のバズワードと言っても過言ではないくらいにブーム化しています。そもそもこのパーパス経営は新自由主義に代わる企業経営のコンセプトを求める欧米企業に端を発しています。
ではこのパーパスとはどういう意味合いで使えばいいのでしょうか?とりわけ「パーパスとミッションと何が違うのか」という戸惑いの声もよく耳にします。パーパスとは簡単に言えば「会社は何のために存在するのか」と「あなたはなぜそこで働くのか」というような社会における存在意義の表明です。事業の直接的な顧客に対してものだけでなく、幅広いステークホルダーとより良く共存している世界を描くことだと思います。
あらためてこのパーパスを最上位にとるPMVV型のコンセプトの定義を以下に示します。
1.パーパス 何のために存在し社会でどういう責任を果たすのかの「志」
2.ミッション パーパス実現のための自社が事業を通じて果たすべき使命
3.ビジョン ミッション実現のための理想の企業像
4.バリュー 社員と共有したい価値観や行動
最近お手伝いをしている中堅企業のトップは、「自社のミッションを社外の人に押し付けるのは抵抗があるがパーパスならしっくりくる」と言われていました。多くの経営層の皆さんは同じようにお気持ちなのかも知れません。
2010年にマーケティングの第一人者であるフィリップ・コトラーが『コトラーのマーケティング3.0』の中で、マーケティングの目的は「製品志向」、「消費者志向」を経て、「世界をよりよい場所にすること」にシフトしていると提唱しました。正直当時はピンと来なかったのですが、10年を経て日本の社会環境も欧米に近づいたこともあって、ようやく実感を持って理解ができるようになりました。とりわけミレニアル世代の中でも1990年代後半から2010年の間に生まれた若年世代のSDGs(持続可能な社会づくり)への意識は高く、実際にアクションを起こしている人も少なくありません。パーパスは採用活動や社員のモチベーションの維持向上に大きな影響を与えるようになってきています。無理して高い給料をもらうよりも、社会課題の解決に寄与する仕事に携わることに幸福感を感じる若年世代。米国ではパーパスを明確にしない企業はもはや生き残れないとまで言われてきており、ここから目を背けていては企業の競争力は低下する一方になりかねません。
「MVVBモデル」はコンセプト策定の切り札
こうしたパーパスが重要視されている現在において、コンセプト策定にうってつけのフレームワークに出会いました。「ビジネスの教科書」で紹介されている「MVVBモデル」です。
MVVBモデルは、「行動⇔目的」と「対外的⇔対内的」の2軸で構成されています。
まずはビジネスの規定から始めます。自社の事業の本質をえぐり出し、将来の変化にもある程度拡張していけるように「ビジネス」をどう規定するかが最重要タスクになります。
この「ビジネス」の規定から、社会的な使命=「ミッション」が見えてくる。
「ミッション」実現のための理想の企業の形=「ビジョン」が見えてくる。
「ビジョン」実現のための仕事をする上での考え方や価値観=「バリュー」が見えてくる。
「バリュー」を判断指標にやるべき事業=「ビジネス」が見えてくる。
PDCAのようにこのMVVBマトリクスを回しながらコンセプトを策定していきます。
このモデルは、どういう事業を展開していくのか「ビジネス」を出発点に置くので、言葉だけが上滑りになることなく企業実体のままを反映したより良いコンセプトになりやすいというメリットがあります。また「ミッション」の部分で、自社のパーパスは何かをじっくり考えることができます。私も実際にビジネスの場面でこのフレームワークを使い始めるようになりました。現代の企業ブランディングにフィットしたものだと思いますので、みなさんも機会があれば一度ぜひお試しください。
[筆者プロフィール]
生山 久展
株式会社TCD ブランディングオーソリティー
戦略開発、調査・分析、商品開発、販促展開まで幅広いブランディング業務に従事。30年余の実務経験をベースに、的確な現状分析から本質的な課題解決のプランニングを得意とする。